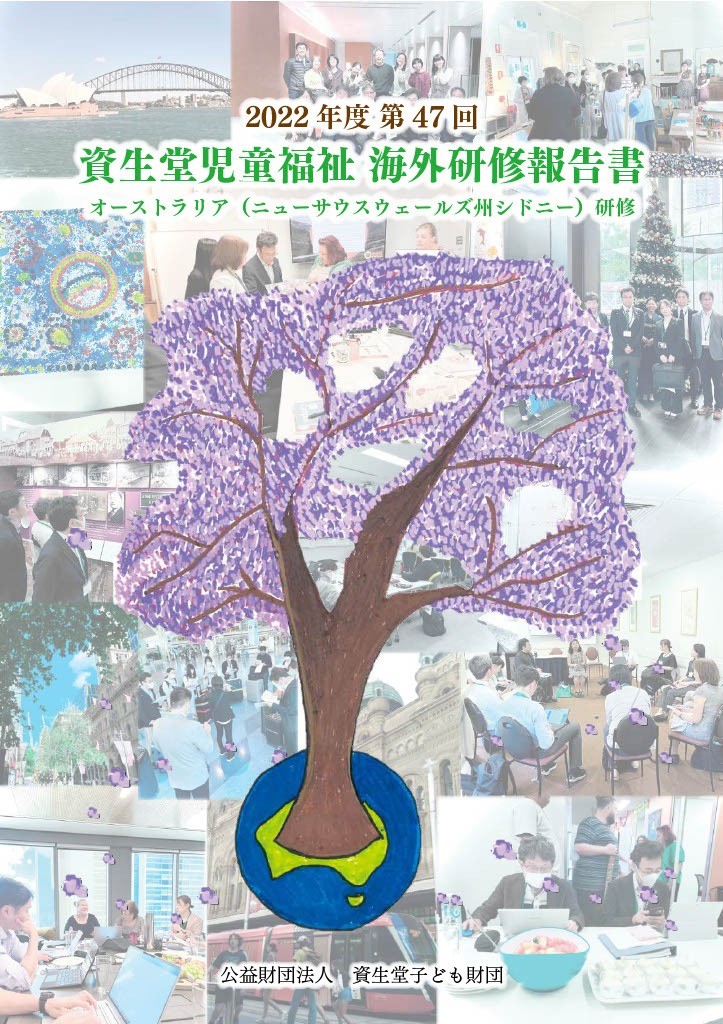第47回
【2022年度】オーストラリア研修

オーストラリアでは、長年、家族や親族、地域の資源をベースにした家族支援を重視してきました。
第47回研修では、ニューサウスウェールズ州シドニーを訪れ、児童虐待の予防・教育サービス、家庭外ケアとなった子どもと家族への支援提供団体、子どもの回復に加え子どものまわりにいる大人の変化も目指した治療的支援団体などを視察し、オーストラリアが標ぼうする多文化主義のもとで展開している家族を中心に据えた児童福祉の制度とその具体的実践を学びました。
また特別企画として、日本でも有名な「サインズ・オブ・セーフティ」の開発者アンドリュ・タネル氏からオンラインでお話をお聞きし、児童虐待対応においての重要な視座をご教授いただきました。
研修参加者は、児童養護施設職員3名、乳児院職員1名、母子生活支援施設職員1名、児童自立支援施設職員1名、児童心理治療施設職員1名、児童家庭支援センター1名、児童家庭支援センター・児童養護施設・子育て支援センター統括所長1名、子どもの虹情報研修センター副センター長兼研究部長1名の10名でした 。研修は渡航研修8日間と帰国後のオンライン研修1回で実施しました。
オーストラリアこども家庭支援の特徴
橋本研修団長は、研修報告書において、①「トラウマケア」「アウトリーチ支援」がサービスの多くの局面で見られたこと、②多機能化されたサービスと高機能化されたサービスが1ヵ所の施設に統合されていたこと、③SofSアプローチが各種支援の土台になっていたこと、④行政からの資金拠出があっても組織として独立性と客観性を維持し、それがイノベーションにつながっていたこと、⑤サービスが提供者の独善的な判断ではなく内省によって客観的に提供されていたことを、オーストラリアのこども家庭支援における基本姿勢やシステムの特徴として挙げています。
またオーストラリアには、先住民隔離政策やイギリスからの児童移民施策などパターナリスティックな政策が展開された歴史があります。こうした過去の失政を政府が認め、被害者や先住民らに謝罪をし、尊厳やアイデンティティの回復のために社会を挙げて取り組もうとする姿勢からは、過ちを未来に向けた価値創造への原動力にしているオーストラリアの姿を見ることができました。しかし同時に、「盗まれた世代」「忘れられたオーストラリア人」と呼ばれるこれら政策の被害者は、家族や言葉、文化とのつながりを失い、今なお多くが深く苦しんでいます。研修では、「盗まれた世代」当事者による「私にとっては“ウェルビーイング”というものが良いものであったことはない」という言葉も聞きました。団員の一人は、支援者側がしてあげたいことが、当事者にとってのしてほしいことではないかもしれないという当事者と支援者の間の見えないギャップがあり得ることを指摘し、「当事者の声を真摯に受け止めることのできる、柔らかな感性を持った支援者となっていきたい」と報告書に書き残しています。
記事作成日:2024年2月

| 訪問州 | 訪問地 | 視察先/講師 | |
|---|---|---|---|
|
ニューサウスウェールズ州 |
シドニー |
NSW州コミュニティ・司法省 |
|
|
NSW州チルドレンズガーディアン |
|||
|
NSW州子ども若者アドボケイトオフィス |
|||
|
Association of Children’s Welfare Agencies(ACWA) 児童福祉機関協会 |
|||
|
The Infants’ Home Child and Family Services 子どもと家族のための多機能型サービス提供機関 |
|||
|
Uniting 福祉サービス提供機関 |
|||
|
Settlement Services International (SSI) 福祉サービス提供機関 |
|||
|
Australian Childhood Foundation(ACF) 子どもと家庭への治療的支援機関 -OurSPACE (part of Australian Childhood Foundation) |
|||
|
Child Abuse Prevention Service (CAPS) 児童虐待防止・教育サービス |
|||
|
CREATE Foundation 家庭外ケア当事者のアドボカシーを推進する組織 |
|||
|
AbSec – NSW Child, Family and Community Peak Aboriginal Corporation 先住民当事者権利擁護団体 |
|||
|
Miho Kobayashi小林美穂氏(オーストラリア認定保育教師) Acting Director of Inner west council early learning centre |
|||
|
西オーストラリア州 |
パース |
Elia Professor Andrew Turnell アンドリュー・ターネル氏(サインズ・オブ・セーフティ開発者) |
※報告書に記された順番、名称や表現に準じて記載
コラム
子どもの安全を守る
第47回研修団員 神戸実業学院 児童指導員 倉成祥子
2022年11月、暖かな春の日差し、咲き誇るジャカランダの花のもと、約1週間のオーストラリア研修に臨みました。
オーストラリアは歴史的な背景もあり、現在は家庭外ケアにおいて施設養育はほとんど行われておらず、里親委託などの家庭的ケアが9割を超えています。こうした状況の中で今回のオーストラリア研修では、家庭外ケアを受ける子どもたちを支援する機関や里親とのマッチングを行う機関、幅広く地域支援を行う機関などを視察しました。研修を通して、子どもの権利をどのように理解しどう守っていくか、アドボカシーをどのように実現していくか、異なる文化的背景をもつ人々がどのように共生していくかなど、これから私たちが向き合っていかなければならない様々な課題について、新たな視点や学びをたくさん得られました。
その中でも私が特に印象的に感じたのは、オーストラリアにおける子どもの安全に対する考え方や制度です。視察先の一つであるCAPSでは、移民や難民を対象に入国後安全に過ごすことを目的としたプログラムsafe arrivalをはじめとし、提供していているプログラム名にsafe〇〇と名付けられたものが複数ありました。また、オンライン研修を行っていただいたアンドリュ・タネル先生が開発者の一人となっているソーシャルワークの技法「Signs of Safety」では、養育者が虐待の事実を認めるかどうかよりも今後子どもの安全が確保される状況にあるかどうかという点に重きが置かれています。
オーストラリアでは、教育機関や地域のクラブチームなども含む子どもに関わるすべての組織が準拠すべき「子どもの安全基準」のもと、すべての活動において子どもの安全を中心に据えるようにと定められています。この「子どもの安全基準」は、視察時点ではこれから本格的に導入されていくという段階であり、子どもの意思が適切に受け止められることや虐待のリスクを最小限にすることなどの10項目の安全基準を、各組織が適切に実施していけるように導入をサポートする仕組みもあるとのことでした。
昨今、子どもの安全が脅かされる悲惨な事件や事故がニュースに取り上げられるのを目にする機会が多くあります。子どもの命を守っていくために、子どもの養育に携わる私たち一人ひとりが日々の養育を振り返りながら、日本社会、日本の文化の文脈に沿ったかたちで、改めて子どもの安全について熟考しその在り方を検討していく必要があるように感じました。
コラムを読む
- 里親制度を学んで 石井公子さん(第6回)
- 福祉の神髄とアメリカンスピリッツ 太田一平さん(第15回)
- 一人ひとりの子どもにふさわしい社会(今) 側垣一也さん(第18回)
- 海外の虐待対応の取り組みから 増沢高さん(第23回)
- カナダから学んだアドボカシー 都留和光さん(第26回)
- 海外研修の意義と意味 中野智行さん(第27回)
- 多民族国家でみた家族を支える支援 麻生信也さん(第29回)
- 米国の虐待防止活動と治療の研修から学んだこと 田中恵子さん(第35回)
- 施設と里親、施設と家族とのかかわり 山高京子さん(第37回)
- 罪を犯した少年や非行少年への支援 関根礼さん(第39回)
- アメリカのエビデンスベーストプログラムとその実践 野々村一也さん(第40回)
- 周産期の母子を支える児童虐待の予防的支援 山森美由紀さん(第42回)
- 日本における児童福祉用語の変遷について 川松亮さん(第43回)
- イギリス児童福祉における協働と連携 工藤真祐子さん(第44回)
- フランスの子ども虐待、児童保護の考え方としくみ 坂口泰司さん(第46回)
- 子どもの安全を守る 倉成祥子さん(第47回)