第46回
【2021年度】フランス研修(オンライン研修)

フランスは、少子化対策の成果が出た国として知られています。第46回研修では、日本が目指す出生レベルにあるフランスにおいて、周産期からの家庭と子ども支援の理念と概要、課題解決のための取り組みを学びました。
また特別プログラムとして、教育虐待や児童保護の経験が綴られた『父の逸脱 ピアノレッスンという拷問』(2017,新泉社)の著者セリーヌ・ラファエル氏(医師)、同書解説ダニエル・ルソー氏(児童精神科医)とのセッションを実施しました。
研修参加者は、児童養護施設職員5名、乳児院職員1名、児童心理治療施設職員2名と施設長1名、子どもの虹情報研修センターセンター長1名の10名でした。
新型コロナウイルス感染症の影響で渡航研修ができなかったため、研修地であるフランスと日本をオンラインで結んだリモート研修を行いました。研修は、エコール・ド・ハヤマ(資生堂湘南研修所)における2泊3日の集合研修を2回と、参加者が自宅や勤務先から参加したオンライン研修3回(研修日8日間)に分けて実施しました。
「虐待された児童」から「危険な状態にある児童」へ
~より広い支援へ
フランスでは、 早くも1889 年に、親権の剥奪に係る規定を含む児童保護のための法ができ、その100年後の 1989 年に新たに児童保護法が制定されました。その後、2007年に制定された児童保護の改革に関する法律では「虐待された児童」という用語を「危険な状態にある児童」と転換し、虐待に限らず、より広い概念でさまざまな問題に対応し、支援しようとする方向が示されました。
日本では児童虐待が社会問題化するなか、2000 年に児童虐待防止法が制定され、深刻な児童虐待への対応に力点を置く方向に舵を切りました。当研修で特別講師を務められた川﨑二三彦子どもの虹情報研修センターセンター長は、報告書で、「日本とフランスでは、対照的な改正方向と考えられよう」とし、児童虐待防止法が制定されてから20年がたち、「日本における虐待対応の歴史に積極的な面が多々あったことを否定する必要はないが、フランスの対応の変遷も参考にし、あらためて児童虐待の問題、また要保護児童の問題について今後のあり方を考えることも、意味があるのではないだろうか」と考察を述べています
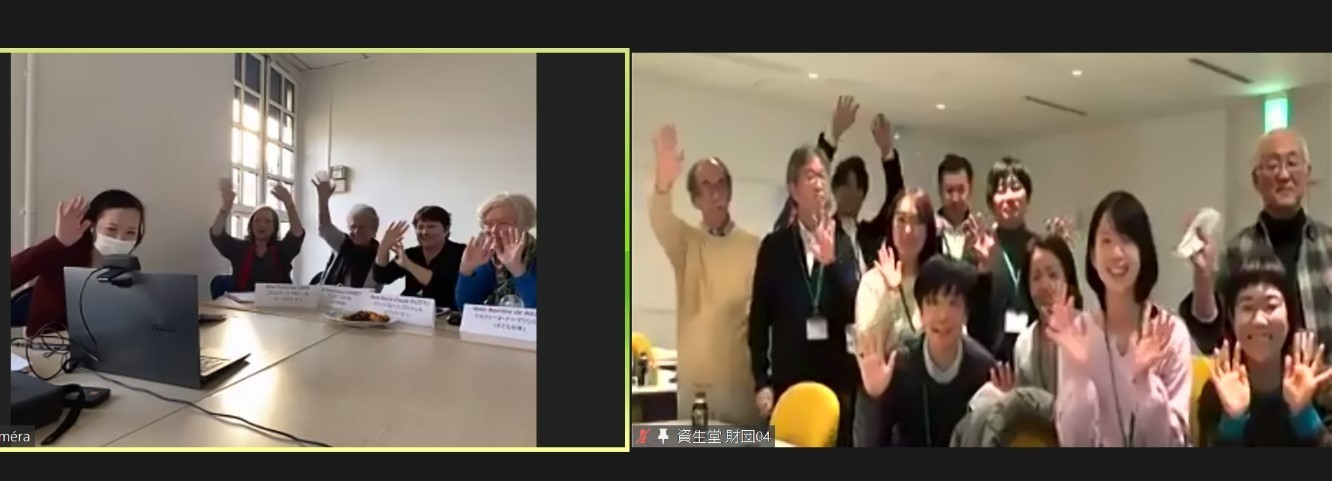
記事作成日:2022年12月
更新日:2024年4月
| 訪問国 | 訪問地 | 視察先 | |
|---|---|---|---|
|
フランス |
パリ |
ODAS地域社会活動国家観測機関 |
|
|
AFIREM児童虐待問題に関する情報提供および調査研究 |
|||
|
GIPED危険な状態にある児童のための公益団体 ONPE全国児童保護観測機関 SNATED危険な状態にある児童のための全国電話相談受付サービス |
|||
|
CRIP75パリ市社会福祉児童保健局 児童福祉課内 憂慮情報収集室 |
|||
|
ANRS全国社会復帰支援協会 青少年教育支援部 |
|||
|
ルレ・アレジア(里親支援機関) |
|||
|
パリ市社会福祉児童保健局 児童福祉課内 子どもの権利と養子縁組事務所 |
|||
|
アルパ‐フィルドール(養親サポート団体) |
|||
|
チルドレンズホーム フォワイエ・メラング |
|||
|
MECS社会的児童ホーム フェリックス・フォール |
|||
|
DPJJ司法省内青少年司法保護局 |
|||
|
UEHC非行少年入所型集団教育ユニット |
|||
|
セーヌ=サン=ドニ |
CER93強化教育センター(非行少年教育施設) |
||
| パリ |
ピエール・ジョルジョ・フラサティ小学校(不登校支援) |
||
|
MDA青少年の家 ソレンの家 |
|||
|
ロベール・ドゥブレ大学病院内移動チーム エキップ・モビール・エスパー |
|||
|
BPMパリ警視庁 未成年保護部隊 |
|||
| アンジェ |
ダニエル・ルソー氏(児童精神科医)(児童保護研究、嬰児殺の歴史) |
||
| パリ |
セリーヌ・ラファエル氏(医師、虐待被害当事者) |
||
|
安發明子氏(フランス家庭福祉研究者) |
※報告書に記された順番、名称や表現に準じて記載
コラム
フランスの子ども虐待、児童保護の考え方としくみ
第46回研修団員 児童養護施設 鳥取こども学園(鳥取) 総括主任・家庭支援専門相談員 坂口泰司
2021年度フランス研修で忘れていけないのは「海外に行かない海外研修」であったことです。団員が実際に会えたのは、事前研修とエコール・ド・ハヤマでの集合研修2回のみ、あとは週末に行われるリモート研修に各自の自宅や職場からパソコンの画面越しに顔を合わせただけでした。またリモート視察で実際に現地を視察できないため、得られる情報も画面を通して見聞きできる情報に限られていました。しかしそうした例外だらけの研修でも、46期メンバーはオンラインの利点を生かした事前調査や交流など、工夫をしながら研修を進めコミュニケーションをとっていました。
さて、フランス研修で学んだなかで最も印象に残っていることは、フランスでは「子ども虐待」を「子どもが置かれた危険な状態」としてとらえ、幅広い概念で支援の網を広げていたことです。保護には行政措置と司法措置の2つがあり、リスク(危険度)の高さと親の同意の有無でその判断がされます。危険度が高い、または親の同意が取れない場合は、司法措置となり、子ども裁判官が判断をして命令を下すことになります。また、同意があった場合でも、親の状況の改善が見られない、支援に積極的でない場合も子ども裁判官の決定になるようです。子ども裁判官は子どもの意見も聴いて措置を決定します。日本とでは、親権と司法関与といった制度の部分でも大きな違いを感じました。
また、児童保護のしくみにおいて「予防・把握」「分析・評価」「保護・支援」の各局面で、専門的な機能を担う施設や機関が置かれ、国家資格を有する専門家が業務を担っていました。一例として、日本の児童相談所で行っている業務は、フランスでは、民間の「虐待通告の受付専門機関(SNATED)」、行政の「アセスメント専門部署(CRIP)」と「措置先選定専門部署(ASE)」によって分担されていました。専門部門が各機能を担うことにより、それぞれの業務内容が明確になり、専門的知識や技術が蓄積されてサービスの質が向上するだけではなく、スタッフのメンタルな負担も抑えられるメリットがあることを学びました。こうした機関は全て古くから存在していたわけではなく、その時々で必要なことは現場の声を聴き、仕組みが作られ、制度改正が行われてきたようです。
視察先の多くの機関や施設で「イノベーション」「実験室」という言葉が聞かれました。「制度がなければ、制度を作る」というように、日本も子どもをまん中にして考え、必要に応じて柔軟に、変化を創生していかなくてはいけないと強く感じたフランスリモート研修でした。
コラムを読む
- 里親制度を学んで 石井公子さん(第6回)
- 福祉の神髄とアメリカンスピリッツ 太田一平さん(第15回)
- 一人ひとりの子どもにふさわしい社会(今) 側垣一也さん(第18回)
- 海外の虐待対応の取り組みから 増沢高さん(第23回)
- カナダから学んだアドボカシー 都留和光さん(第26回)
- 海外研修の意義と意味 中野智行さん(第27回)
- 多民族国家でみた家族を支える支援 麻生信也さん(第29回)
- 米国の虐待防止活動と治療の研修から学んだこと 田中恵子さん(第35回)
- 施設と里親、施設と家族とのかかわり 山高京子さん(第37回)
- 罪を犯した少年や非行少年への支援 関根礼さん(第39回)
- アメリカのエビデンスベーストプログラムとその実践 野々村一也さん(第40回)
- 周産期の母子を支える児童虐待の予防的支援 山森美由紀さん(第42回)
- 日本における児童福祉用語の変遷について 川松亮さん(第43回)
- イギリス児童福祉における協働と連携 工藤真祐子さん(第44回)
- フランスの子ども虐待、児童保護の考え方としくみ 坂口泰司さん(第46回)
- 子どもの安全を守る 倉成祥子さん(第47回)





